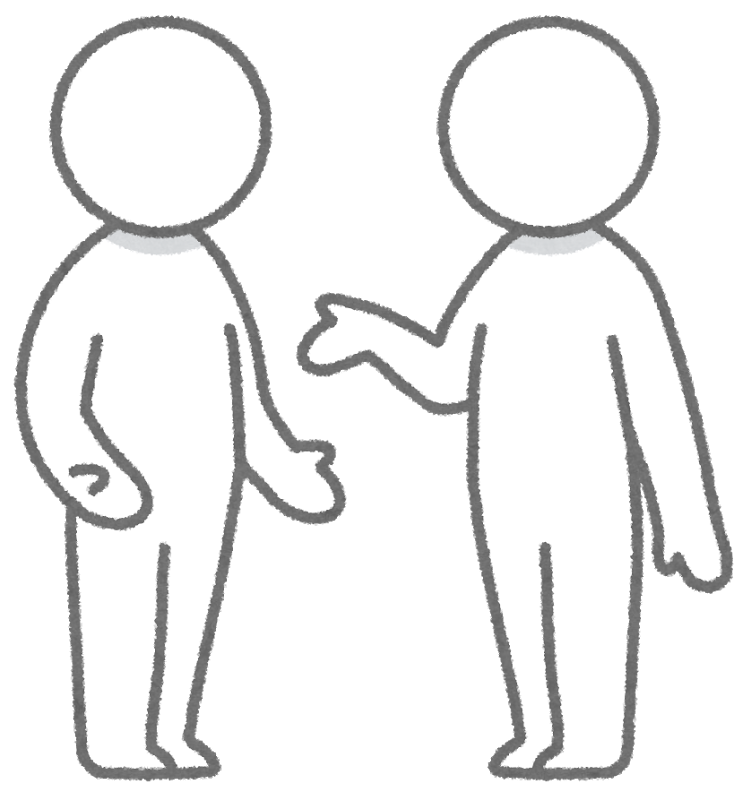私の祖母は耳が非常に遠く(難聴)の上に認知症でつい数十分前のことも覚えていません。そんな祖母とどうやってコミュニケーションをとっているのか、その方法について書いていきます。
仕草(ジェスチャー)や口パクで対応する
まず1つめは、仕草(動作)や口パクである程度分かってもらう方法があります。
例えば、何かをお年寄りから言われたときに、YESなら頷く、NOなら頭を横に振る、分からないなら首をかしげる等です。これだと、少なくともYES/NOの意思表示は可能です。
また、ダメなことをしている場合は、両手でバツ印を作るといったジェスチャーでも意外と通じます。
後は、普段使っている簡単な単語だけなら口パクでも分かってくれます。
例えば、「ごはん」とか、「ダメ」とかです。このときは、普段しゃべっている時よりもしっかりと大きめに口を開けて、祖母が見ているのを確認しながらゆっくりと口を動かすと上手く行きます。声は出さなくても結構伝わりますよ。
逆に手話のような真似ごとをしてもいまいち上手くいきません。まあこれは当然ですよね。祖母がそもそも手話を全く知らないのですから。
こちらからは筆談で対応する
上記の方法だけでも、ある程度の意思疎通はできるのですが、YES/NOでは答えることのできないことや、普段使っている単語以上のことを答える必要がある場合は、筆談で対応しています。
祖母は筆談ではなく普通に喋って、その回答を私が紙に書いて見せる、というやり方です。
筆談のメリット
この方法の良いところは、祖母が読んである程度理解をしてくれる点と、書いた紙を保管しておくと、同じ質問を受けた時にまたその紙を渡すと解決する点です。
要するに、何度も何度もこちらが答える必要がないのでストレスの軽減にもつながります。
実際、この筆談形式を使いだしてから、私の祖母に対するストレスはかなり軽減されています。聞いてくる話の内容も、大体同じようなことばかりなので紙が10種類もあれば十分対応できます。
もしも、難聴で認知症のお年寄りに、何度も何度も同じことを聞かれたりして、そのたびに大声で答えを教えるけど、本当に聞こえているか分からないし、なかなか理解してもらえない…
みたいなことに疲れたり、イライラしたり、ストレスになっている人がいたら、ぜひ筆談を試してみてください。ポイントは、一度説明に使った紙を保管しておくことです。
本当にストレスの軽減につながりますし、わざわざ大声を出すよりもお年寄りが理解してくれる可能性が高いと思います。
少なくとも、私の祖母に対しては効果が絶大です。(残念ながら目が悪い人には対応できませんけど)